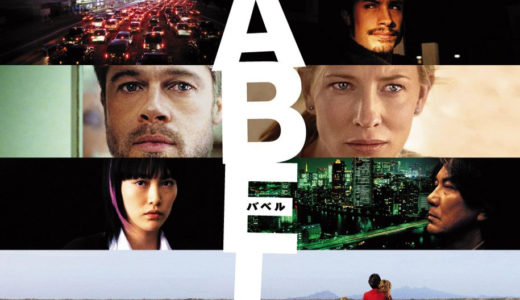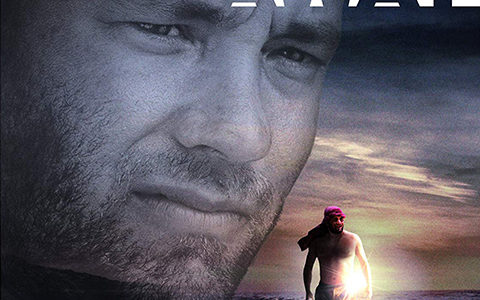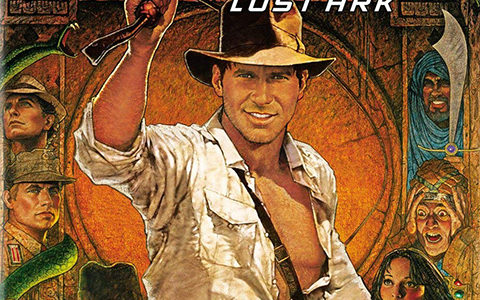はじめに
今回は2016年公開の映画『レヴェナント:蘇えりし者』について考察してみました。
この映画はアメリカの西部開拓時代に実在したヒュー・グラスという人物を扱った物語です。
主演はレオナルド・ディカプリオで、見事アカデミー賞の主演男優賞に輝いています。
さて、この記事では映画『レヴェナント:蘇えりし者』を自分なりにレビュー・解説しています。
独自に『レヴェナント:蘇えりし者』を考察しているので、この記事と合わせて見てもらえば、より深く作品を味わうことができるでしょう。
大自然の中で生と死の狭間で生きる、迫力たっぷりの男を見られます。ぜひご覧になってください。
レビュー・解説にあたって
当ブログの映画ページでは、映画の魅力をより伝えられるように、私の視点で映画の中身について語っています。(ネタバレ含みますのでご注意を!)
例えばこのシーンを見ると、より感情的な配慮があったり、技術的に訴えているなどの意味合いなど、細かい部分などにあたります。もし、お手元に映画があるなら一緒に見てもらえると、より分かりやすいと思います。
それでは始めて行きます!
映画の概要
スタッフ/キャスト
- 監督:アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ
- 脚本:マーク・L・スミス、アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ
- 出演:レオナルド・ディカプリオ、トム・ハーディ
- 撮影:エマニュエル・ルベツキ
- 音楽:坂本龍一、アルヴァ・ノト
- 公開:2016年
あらすじ
1823年の西部開拓時代、アメリカ北西部の極寒地で狩猟を生業としていた者たちがいた。
その中にとある親子がいて、その子供が、傷を負った父親を守るために仲間に殺されてしまう。
父親であるヒュー・グラスは、傷だらけの身体で息子を殺した男を追い始める。
手持ちカメラが見せる驚異の空気感
オープニングで、森林の中、動物の毛皮を剥いでいるアメリカ人たちがいます。
しかし、そのアメリカ人たちは何の前触れもなくいきなり殺されていきます。

どこからか放たれた矢がアメリカ人の体を貫いたり、勢いよく馬に乗って走ってきた人物からヤリで突き刺されたりです。
攻撃している相手は、最初は誰かは分かりませんが、その後アメリカン・インディアンであることが段々と知らされていきます。
その、無残にも人が倒れていく光景は見るに耐えないほどです。
そんな、もはや戦争と変わらないと思えるほど、狂気と悲惨な光景から『レヴェナント』の幕が明けていきます。
激しい戦いから始まることで、この映画が生易しい物語ではないということが最初から示されています。
そして、この映画で注目すべき表現手法も物語の最初から最後までおこなわれています。
それは、カメラがほとんど「手持ち」だということです。
風景と状況を見せるエスタブリッシングショットや静かなシーンを除いて、主要なアクションを起こしているシーンでは、カメラマンがカメラを手持ちで撮影しています。
そして、手持ちと言ってもブレないようにステディカムという機材などを使ったり、反対にあえてブレさせたりもしています。
また、その際に望遠レンズは使わず、広角レンズが多用されています。
広角レンズの場合、望遠レンズと比べ当然ながら遠くのものは遠くにあるようにしか映らないので、基本的に撮りたい被写体には少しでも近づく必要があります。
そのため、登場人物を広角レンズを使ってクローズアップで取ろうとすると、かなりカメラが役者に近づかなければなりません。
このレヴェナントでは、被写体となる登場人物(役者)とカメラの間はとても近い距離になっています。

レンズの焦点距離やシーンにもよりますが、おそらく最もクローズアップしている(近づいている)時は30cmも離れていないでしょう。(ぶつかったりもしていますしw)
これだと役者にとっては、ほぼ目の前にカメラがあるのと同じ状況になります。
撮影監督が考えたフレームとその動きに応えるカメラマン、そして何よりカメラが目の前にあるという状況の中で、役者たちの自然な演技に驚くばかりです。
こうした表現手法を多用することで、最後までこの映画の迫力と並々ならぬ緊張感がずっと維持されていきます。
『レヴェナント』を見た後は、誰もが消耗して疲れを感じることになると思いますね。
本物? CG? 壮絶な熊との戦い
オープニングのアメリカン・インディアンから逃げることが出来て、船を捨てたところです。
これから歩いて砦に向かう前に仲間たちは休んでいます。
ヒュー・グラスは朝早めに起きて、森の中を斥候(せっこう:「偵察」のこと)しにいきます。
ここで思わぬ相手に遭遇します。

アメリカン・インディアンではなく、とても大きな熊(グリズリー)の親子です。
そして親熊はグラスを一目見ると、一目散に走りながらグラスに襲いかかりました。
グラスは銃を構えようにも熊の方が走るのが早く、撃つことが出来ずに一瞬にして倒されます。
その後、グラスは徹底的に痛めつけられます。
熊が爪で引っ掻いたり、噛み付いたりなどです。
この光景が半端ではありません。
壮絶であり痛々しく、またもや目を覆いたくなるほどです。
まさに熊の攻撃とはこういうものなのだろうと感じさせてくれる迫力があります。

そして、すごいのはこれが実写にしか見えないというところです。
熊の着ぐるみやCGなどを全く感じさせないのです。
「もしかして本物の熊?」と一瞬思いますが、「それだったらカメラマンも襲われているのでありえないなw」と一人で余計な納得をしてしまうほどリアルさに満ちています。
おそらく着ぐるみにCGを合成させているのだろうと思うのですが、それにしても精巧に作られているので素晴らしい迫力が伝わってきます。
また、グラス(ディカプリオ)が熊に対し、なす術もないという演技を見せつけてくれます。
フィクションとは言え、こんなのを見たらだれも熊には襲われたくないと思うでしょう。
迫真の演技とノーカットによる演出効果
息子がフィッツジェラルドに殺されたあと、何とかグラスが這いながら川を見つけ、水を飲もうとしたシーンです。

川の水を口に入れて飲み込もうとすると、突然むせてしまい吐き出します。
吐き出した液体の中には血も混ざっていました。
これは、熊に攻撃されたためのどが傷ついているからでした。
このため、グラスはのどの消毒とを併せて傷を塞ぐために、火薬を使おうとします。
そのやり方は、のどに火薬を塗り、そののどの近くに火を持って行ってわざと発火させるというやり方です。
考えただけで恐ろしいシーンです。
しかし、その恐ろしいシーンの撮影が見事なのです。
それはグラスが「火薬をのどに塗り」、「火打石を使って火を起こし」、「そしてその火をのどに持っていき」、「気絶して倒れる」まで、一部編集点はあるもののほぼノーカットで最後まで収められているのです。

つまり、ディカプリオはこのシーンを止まらずに演じきっているのです。
正直、グラスというよりも「ディカプリオ」本人を心配してしまいます。
そしてカメラマンは、その演技を一部始終を止めることなく収めています。
とんでもないシーンです!
まぁただ、実際に火を起こしているのはカメラの左側にいるスタッフであり、実はその人がつけているのが何となく分かりますし、首周りは傷がついた特殊メイクの皮膚を張っていて、傷がつかないものになっているとは思います。
しかし、それでもディカプリオの役者魂に感嘆せざるをえません。
そして、これをノーカットでやったところがすごいです。
それもそのはず、この場面でいちいちカットして編集するわけにもいきません。
ここでは、グラスが何を始めるのか?という緊張感を観客にずっと維持させたいからです。
そこに下手な編集を施すよりは、ノーカットで一部始終を見せた方が効果的です。
観客の「まさか、まさか…」という感情を引き起こさせるには、この見せ方の方が優れています。
そして、それを本当にやってしまうのですからすごいのです。
また、このあとにも出てくる、グラスが魚を食べるシーンでも同様にノーカットで見せています。
レンズ越しという表現をあえて使う演出の真理とは?

『レヴェナント』では、登場人物の吐く吐息がレンズにかかることを無視しているのに驚きます。
映画だけでなく、どのような映像表現でもレンズが曇ることなどは基本的にご法度です。
そんなことはやってはいけないのです、というのが今までの通例でした。
その理由は、そんなことをしてしまうと目の前の映像がカメラを通して見ていることになり、それが観客に伝わってしまうからです。
映像表現もとい、カメラマンは、見ている人にカメラで撮っていることを感じさせないようにすることが一つの使命です。
どのようなカメラマンも目の前で起きていること(演出)を自然に捉え、それをそのまま観客に見て感じてもらえるようにと考えます。
したがって、カメラマンは「カメラという存在」を可能な限り消すことを目標に撮影します。
ところが、このレヴェナントではレンズに吐息がかかるどころか、水や雪、血しぶきなども付きます。

こうして、観客にレンズを通して見ているということをあえて感じさせています。
なぜこのような手法にしたのでしょうか?
おそらくこれは、もはや現代人がカメラで動画を撮影することが当たり前になっていて、カメラが被写体を捉える(撮影する)ということ自体に、違和感を感じることがないからだと考えます。
現代では、昔のようにカメラや撮影に関する専門的な知識や技術も、もはや必要ありません。
誰でもスマホで動画を撮れてしまい、また撮った動画をいつでもネット上に上げることができるので、動画自体が身近に感じられるものになっているからです。
だから、レンズに何かが付着しようが、特に誰ももう気にしない時代になってきているのです。(ゲームではレンズ越しの表現が当たり前になってきますしね)
しかし、もちろんそれだけの理由ではないでしょう。
私はスマホ動画に対するアンチテーゼとしても感じられます。
この映画の作り手は、逆説的ですが「どうだ見たか!?映画ってのははここまでやるんだ!!ここまでやってこそが本当の撮影なんだ!!」と言っているようにも感じるわけです。
この監督である「アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ」と撮影監督である「エマニュエル・ルベツキ」は、とても素晴らしい表現力を持っていると言わざるを得ないでしょう。
正直、吐息や雪、血しぶきが仮にCGだとしてもそれはどちらでもよく、圧倒的な臨場感を感じてもらうためにこのような表現をしているのです。
そしてそれは、グラスが必死に生きようとする姿を、まざまざと見せつけてくれていることに成功していると感じます。
観客に忘れさせない主人公の目的
グラスが、必死に砦や仲間の元に戻ろうとしている旅路の途中で、「フィッツジェラルドが息子を殺した」と岩や雪に書いています。

これはなぜでしょうか?
単純に、観客が「グラスが、息子を殺されたことを忘れないようにとしているのだろう」と考えるのが妥当ではあります。
しかし、それだけではありません。
これは、わざと観客にグラスの目的を暗に知らせているのです。
グラスは何度もひん死の状態に陥ります。
そして、アメリカン・インディアン、フランス人、砦の仲間たち、家族の夢など色々な情報が映されていくので、観客にとっては何となくグラスの目的は何なんだ?という思いに陥りやすいのです。
それもそのはずで、グラスと会話する人物があまりにも少ないからです。
途中で出会った、バッファローの肉を分け与えてもらったインディアンは、グラスを助けたのちにすぐにフランス人に殺されてしまいます。
このため観客には、グラスが必死にサバイバルをして生きようという意思は感じますが、その心についてはほとんど読めないのです。
だからこそ、あえて何かに書くことによって観客に目的を再確認させているわけです。
書く内容は「フィッツジェラルドが息子を殺した」とし、「フィッツジェラルドを殺す」にはしません。
「フィッツジェラルドを殺す」と書いてしまうと、グラスはただの殺人鬼に成り下がってしまうからです。
だからこそ、あえて「息子が殺された」と書き、観客にはそのことを思い出させています。
こうすることで、グラスの復讐心を観客と共有させているわけです。
2時間半にも及ぶ長い映画であり、会話がない主人公の物語だからこそ必要であり、効果的な手法です。
リアルな戦いはついにここまできた!
最後のグラスとフィッツジェラルドが戦うシーンです。
ここも過酷で過激な戦いを見せてくれます。
すでにお互い重傷を負った身で、「復讐を誓った者」と、「罪から逃げてでも生きようとする者」たちの戦いだからです。
お互いがどんどん近づくことで緊張感が盛り上がり、観客は逃げ場のない張り詰めた空気を感じることになります。

ここまで来ると、もはやどちらかが生き、どちらかが死ぬしかないと分かります。
そして、このシーンも素晴らしいものになっています。
カメラは手持ちで、何より特段の長回しをしているからです。
編集点がいくつかあるので、おそらくこのシーンは何度かは撮影しているとは思います。
しかし、二人が鉢会ってからフィッツジェラルドが倒れるまでは、ほぼノーカットで撮っているのでしょう。
二人の戦いの間に無駄なカットがないからです。
あまりに自然な流れです。
ここまでやれるのが本当にすごいです。

しかも、演技として見ても二人が戦いで傷ついていく様には目を見張ります。
当然、戦いなので血が出てきますが、その血が本当に自然のように見えるので撮影上どうやって出しているのかは首を傾げるしかありません。
また、ナイフでグラスの手を刺したりフィッツジェラルドの足を刺したりしていますが、どう見ても本当に刺しているようにしか見えないのです。
一体これらをどうやって演技させ撮影をしているのか理解を絶しますが、「戦いを描くレベルがものすごく高い」ということだけは言えると思います。
そして、最後にグラスは「復讐は神の手に委ねる」と言い、まだ息があるフィッツジェラルドを川に流します。
見た目緩やかな川ではありますが、そのまま流されてしまう可能性は否定できません。
しかも極寒の川です。
それでも川に流す演出をするのです。
グラス役のディカプリオもそうですが、フィッツジェラルド役のトム・ハーディもよくやるなと思いますね。
演出と演技が迫真すぎて、最後まで驚嘆されっぱなしです。
まとめ
緊張感と緊迫感、そして圧倒的なリアル感。
また、現代では考えられないほど徹底的なサバイバル感。
映画『レヴェナント』では大自然のなかで傷を負ったものがどう生き延びるか、そして復讐のためにどう動こうとするかという、強き意志を見せつけてくれます。
加えて、坂本龍一氏の音楽もまたその世界観を美しく表現してくれています。
アクション映画のように重々しい旋律ではなく、どこか儚げで寂しさを感じさせてくれる音楽です。
大きな盛り上がり感はありませんが、それでも胸が締め付けられるような緊張音がずっと続き、とても印象的です。
戦いに勝利したグラスは最後にカメラのレンズをじっと見つめます。
これは、ずっとグラスのそばにいた私たち観客へのメッセージです。
様々な感情が含まれているとは思いますが、「人とは何か、生きることとは何か」を私たちに問うているように感じられます。