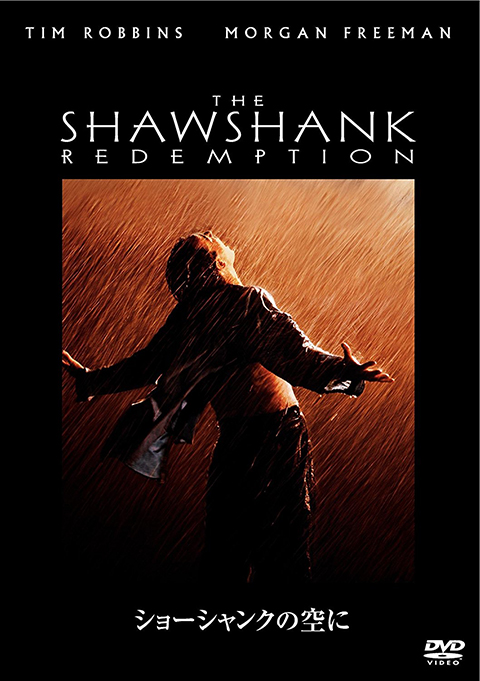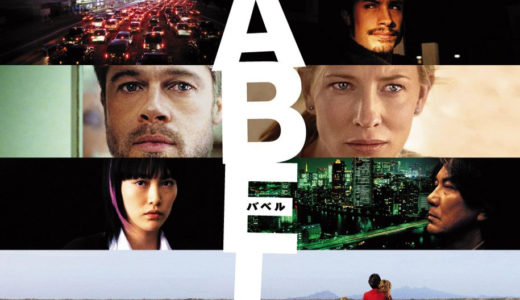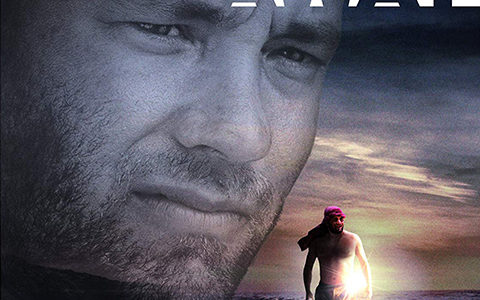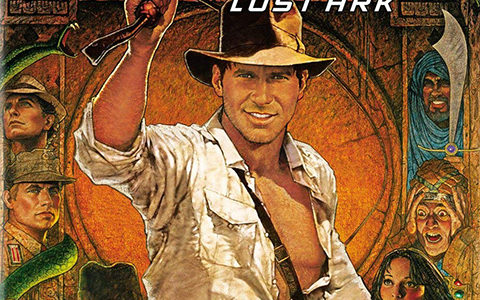はじめに
今回は『ショーシャンクの空に(The Shawshank Redemption)』の解説です。
ネタバレしていますので、読む際はお気をつけくださいませ。
映画の概要
あらすじ
アンディ・デュフレーンには愛する妻がいた。
しかしその妻には隠れた愛人がおり、アンディはその情事を知ってしまう。
自暴自棄になったアンディは、怒りを持って銃に弾を込める。
妻と愛人が地に倒れると、アンディは容疑者として起訴され裁判にかけられる。
アンディは「自分ではない」と無罪を主張したが、状況証拠から見てアンディの犯行に疑いの余地はなかった。
判決は無期懲役。
失意の底に落ちたアンディは刑務所に入れられ、10数年の時を過ごすことになる。
時が大きく巡る中で、真実を想う心を胸に秘めながら、アンディはひたすら静かなる戦いを進めていた。
キャスト・スタッフ
| 出演者 | ティム・ロビンス、モーガン・フリーマン |
|---|---|
| 監督 | フランク・ダラボン |
| 原作 | スティーヴン・キング |
| 脚本 | フランク・ダラボン |
| 撮影監督 | ロジャー・ディーキンス |
| 編集 | リチャード・フランシス=ブルース |
| 音楽 | トーマス・ニューマン |
| 公開 | 1994年 |
冤罪という社会的制裁の影
『ショーシャンクの空に』は、1947年を舞台にして冤罪という大きなテーマを扱っている。
映画ではかなり過去の話ではあるが、実際、冤罪自体は21世紀になってもまだその影をひそめることはない。
しかも、科学技術の発展により、過去には立証できなかった証拠が改めて見つかることによる生まれる冤罪も存在している。
これを仕方がないことだと一掃してしまうのは簡単だが、その容疑を受け有罪判決が下った人々の心の内を想像すると、誰の目にも残酷すぎると思える悲劇であり、私たちが同情することさえもおこがましくなってしまう。
ちなみに、2001年から2019年までの日本全国の確定無罪による冤罪件数は、23件とのこと。
参照:雪冤プロジェクト
これを多いと見るか少ないと見るかは統計的な観点と警察による操作手順などを含め、様々な視野から見る必要があるが、問題はこうして無罪の人が容疑にかけられている実情があるということだ。
しかも、これが正しい数値ではないことも同様に考えられる。
今現在刑務所に入所している人たちの中にも、冤罪の人がいる可能性は捨てきれない。
現に、再審により無罪となったケースが多々あるからだ。
犯罪が常に横行する中で、私たちには、警察による操作と法制度、裁判がきちんと機能していることを信じるしかないというのが実情なのである。
観客誰もが引き込まれる秀逸なオープニング

『ショーシャンクの空に』のオープニングも映画史に残る名オープニングだろう。
主人公であるアンディは、夜空さえも森林の木々に囲まれてしまうような暗い場所にひっそりと佇む一軒家の前で、車のカーステレオのラジオで音楽を聴きながら悲壮感を漂わせている。
ふと意を決したかのように手を伸ばした先には、包みに銃と散らばった弾丸がくるまれている。
それを膝の上に載せながら、アンディは小脇に抱えた半分以上飲み干した平たい瓶の酒をまた一口飲み、険しい表情を見せる。
そして、舞台は裁判所に変わる。
検察の担当官からアンディと妻の生活スタイル、そして妻と愛人との関係が赤裸々に語られ始めながら、車にいるアンディのシーンに戻ると、銃のリボルバーに弾を込めるアンディ。
検察からは、妻と愛人が38口径の銃弾により殺害されていたことが告げられるも、アンディ自身は、銃は川に捨てたと語る。
しかし、その捨てられた銃は発見されず、アンディにはあまりにも都合がいいと検察から言い放たれてしまう。
そして、検察から殺害状況を説明する声が同時に流れる中、アンディの妻と愛人による性行為が映し出される。
観客は頭の中で『バイオレンス』を想像しながら『エロティック』な情景を前に、二つの感情が絡み合いながら何とも言えない感覚に支配される。
そして、もっとその情事を見ていたいと思う観客(男)を尻目に、画面には高齢な裁判長が映されアンディには無期懲役という有罪判決が言い渡される。
ここまでたった5~6分程度だろうか。
見ている観客は、アンディが犯人だとは思いにくい。
しかし、アンディが嘘をついている可能性も捨てきれず、状況証拠からいって犯人ではないと言い切ることもできない。
作り手から、全く判断が付かない大きな疑問をわずか6分ほどで観客に持たせられたことになる。
ここまでシーンはわずか『車に乗ったアンディ』『裁判所』『妻と愛人』の三つしかないが、観客はすでに映画に引き込まれてしまっているわけだ。
『ショーシャンクの空に』のオープニングは、素晴らしく練られ、とても優れたシークエンスであり、これだけでご飯3杯はいけてしまうw
レッドという大きな語り手の存在
オープニングが終わると刑務所内にいるレッドが語り始める。
主人公はあくまでアンディだが、そのアンディについての性格や行動を掘り下げていく役目を負っているのは、今まで一度も出会ったこともなかった赤の他人であるレッドという構成が面白い。
このようにすることで、どちらかというと寡黙なアンディと観客との間に、橋渡し役という役割をレッドが担ってくれ、当のアンディが持つ大きな秘密を隠すことに一役買っている。
作り手は、アンディにはとてつもなく壮大で秀逸な企みがあることを、観客の目からわざと背けさせているわけだ。
そして、重要なのが、生きてきた背景が全く違うレッドという人物がアンディについて語ることで、アンディを贔屓なく完全に第三者からの目線で見せられることだ。
そのおかげで、観客も一歩アンディから距離を引いて見られるので、アンディが本当に殺人を犯した犯人なのかどうかが見定められる。
また、比較的活発なレッドとは違い、生気があまり感じられないアンディのなんとも言えない雰囲気や仕草などに、観客は思いをはせることもでき、感情移入を高められる。
そして、レッドにそれだけの大役を任せるだけでなく、さらに重要な役柄も持たせている。
それはレッドには、仮釈放がなかなか認めてもらえないというジレンマがあることだ。
このジレンマのせいで、レッドは生き方を模索せざるを得ない。
ところがアンディが来たことで、アンディの生き方に影響を受けることになる。
そして、それはレッド自身の心に変化をもたらすことになり、その結果最終的には仮釈放が認められることになる。
また、同時に最後は危険だと心に蓋をしていた『希望』という言葉を見直すことにもつながる。
アンディはレッドに救われ、レッド自身もアンディに救われる秀逸な物語設定である。
囚人たちの中で「アンディ」と「レッド」を分かりやすく見せるには?


これは見せ方の問題であり、ビジュアルデザインという分野になるが、見過ごせない点がある。
映画など画面内に人物を目立たせる、つまり主人公のような重要な存在感を分からせるには、画面の中にどれだけその人物が占めているかを測ればいい。
故に、重要な人物は、画面内に比較的他の人物や物よりも大きなスペースを取らなければならない。
これは、登場人物が少ない際には特に気にすることもないものだが、多数の人物が画面を支配する場合、また、その登場人物たちが皆同じ格好をしている場合は割と大きな問題として浮上してくる。
なぜなら、登場人物たちの区別がそれぞれ付かなくなるからだ。
ショーシャンク刑務所は読んで字の如し刑務所であり、皆囚人服を着ている場所だ。
誰一人として例外は許されず、グレーの下地に縦のストライプが入ったYシャツと紺のズボンだ。(紺の上着もあるにはある)
そのため、服の着方にそれぞれ個性を持たせることはたやすいが、それでも刑務所内にいる人間たちの多くに区別をつかせることは難しい。
数が多ければ多いほど人物の存在感は薄れていってしまう。
増してや、刑務所内の囚人たちは全員が男であり、女性の影は一切ない。
男の中から女一人を見つけるのは簡単だが、男の中から特定の男を見つけるにはとても難しいのは言うまでもない。
そうなると、撮影する際に囚人たちの中から『アンディ』と『レッド』をどのように目立たせるか?と言う問題に出くわす。
『ショーシャンク』は、アンディとレッドを軸に展開していくことになるので、群衆の中でアンディとレッドが一目で分かる必要がある。
もちろん、その点は作り手も重視していて、きちんと二人が目立って映し出されるようになっている。
では、これには何かトリックのようなものがあるのだろうか?
実はその方法はとても簡単で、意外にも単純な方法で解決が図られている。
それは『アンディ(ティム・ロビンス)』と『レッド(モーガン・フリーマン)』は元々背が高いのだ。
背が高ければそれだけで十分目立つので、誰が見ても一目瞭然であり、画面内のスペースを占拠しやすい。
スペースを占拠すれば、当然その人物に目が行きやすい。
たったこれだけであり、拍子抜けするようなことである。
あなたも肩透かしを食らって「はぁ?何だよ!」と思ったかもしれない。
ところが、このような基本的な身体的特徴というのは、この映画のような条件に左右された場合には大きく功を奏すことが分かる。
俳優選びのキャスティングディレクターの腕の見せ所になるのは間違いない。
そして、これらのことを頭に入れながら撮影監督と監督が考えることは、背の高さをさらに強調させることだ。

つまり、室外のシーンでは、よりその高さを強調するように、あえて仲間たちを低く見せていることに気づく。
たかが身長ではあるが、人物の背の高さそのものの特性を利用することでビジュアル・デザインとして機能させている点に注目したい。
また、レッドについては目立つ点として黒人だという事実もあるにはあるが、仮に黒人でなかったとしても身長が高い人物を起用したのは間違いないだろう。
アンディはなぜレコードをかけたのか?

アンディは元銀行の副頭取であり、看守主任であるハドレーの所得申告を代わってやったことで、所長から一般的な肉体労働ではなく図書室と会計の仕事を任せられることになった。
そして、アンディは自ら多くの本を集めるべきだと考え、州議会に手紙を毎週送るようにする。
では、アンディはなぜ本をより多く欲したのだろうか?
アンディは銀行の元副頭取という職業上、それなりの見識を備えていることは明白だ。
ともすれば、その知識を得るに値する道具として最適なものはもちろん本だと考えるのは間違いなく、その本が持つ力というものを当然ながら知っているのは疑うまでもない。
アンディ自体、台詞の中から本から得た知識を発していることからもそれは分かる。
であれば、その偉大な本の力を皆と共有したいと願う気持ちを持つことも不思議ではない。
これもまたアンディというキャラクターの一つの表れであると言える。
そうした気持ちを持ち続けた結果、アンディは6年という歳月を費やすことにはなったが中古図書と州議会からの予算を獲得することに成功する。
ここで分かるアンディのもう一つの事実に注目しておくと、アンディは実に絶え間ない努力家であるということだ。
さて、中古図書を受け取ったシーンに戻ると、アンディは不可解な行動を起こす。
まず、アンディは中古図書として箱に入っていた中に音楽用のレコードを見つける。
アンディはずっと図書予算だけを希望していたのだが、まさか中古図書に加えレコードも寄付されるとは思ってもいなかったのだろう。
すると、看守がトイレに行ってそばにいないことを良いことに、アンディはそのレコードをプレーヤーにかけてしまう。
当然、音楽がその部屋内に鳴り響くことになるが、それだけでは飽き足らず、アンディは刑務所内すべてに聞き渡るように館内マイクでレコードの音を拾うことまでする。
観客は当然ながら「そんなことをしたら…」と気が気ではない。
しかし、当のアンディには少し罪悪感を見せつつもその表情には笑みが見える。
ショーシャンク刑務所のサイレンから鳴り響くその音楽に、レッド含む囚人たちは動揺の色を隠せず、ぼーっと微動だにせざるを得ない。
そうこうしている間に所長以下、ハドレーや看守が駆けつけアンディを取り押さえることになる。
そして、その行為の代償として二週間の間、懲罰房に入れられることになってしまう。
さて、ここで疑問が生まれる。
なぜ、わざわざ罰を受けるだろうということを分かっていながら、アンディはレコードをかけたのだろうか?
まず音楽面から考えてみると、レコードのタイトルは『フィガロの結婚』だった。
この『フィガロの結婚』はオペラであり、その内容は貴族に対する痛烈な批判が込められているとのことだ。
となると、図書予算が下りるまでに6年もかかった州議会への体制や、今いる刑務所に対しての批判ととらえてもよさそうである。
また、ここまでに起きた仮釈放を許可された元仲間の老人ブルックスの自殺に対するやるせなさなどもあるかもしれない。
しかし、本当にアンディはそこまで考えていたであろうか?
アンディは中古図書を受け取った時も、レコードをかけている時も笑顔を見せていた。
この笑顔は、レッド含む仲間たちと共に屋根の修復作業をおこなった際に、鬼主任であるハドレーの所得申告を申し出て、その見返りのビールを皆にご馳走した時の笑顔と同じものだ。
その時のレッドはこう語っている。
アンディは「安らぎを求めたんだろう」と。
つまり、レコードをかけたアンディは、自分のこれまで行ってきた正当性とそれが達成できたことについて、天にも昇るような夢心地をただ単に刑務所にいるみんなと共有したかった、皆と音楽を聴いて喜びを味わいたかっただけだと考える方が自然だと言えよう。
きっとアンディも、レッドと同じように自由な時間を味わいたかったのだろう。
アンディらしさを垣間見せる一幕である。
しかし、それと同時に、アンディにはある一定以上の感情が沸き立つと、それを抑えきれない性格であるということも表しているのは確かである。
復讐をしなかったアンディ

もし仮にこの映画がアクションやサスペンス映画なら、間違いなくアンディが真犯人を復讐する映画になったはずだ。
アンディは早々に脱獄し真犯人を追いかけ、裁判長すら襲っていくような内容の映画である。
そして、この物語では結果的にアンディは脱獄に成功することになる。
つまり、映画的な尺の問題は置いておいて、アンディには復讐を視野に入れた行動も可能であったはずだ。
しかし、そんな安っぽい物語にはせずに、『ショーシャンクの空に』は感情を揺さぶる崇高な物語になっている。
ここで、アンディが真犯人を知ることになるシークエンスを思い出してみる。
アンディが図書予算をさらに獲得できるようになり、図書室の改装まで可能になった後、トミーという若い囚人がショーシャンク刑務所に2年間服役することになる。
そしてアンディとレッドはそのトミーから、アンディの妻と愛人殺しの真犯人の話をたまたま聞くことになる。
その犯人はエルモという名の男で、愛人の家に盗みに入った際に、アンディの妻と愛人を殺したというのだ。
奇しくもその日がアンディが犯行に及ぼうとした夜であり、アンディにとっては全くの偶然の一致に他ならなかった。
そして、それを聞いたアンディは、ようやく汚名が晴れると信じ、すぐさま所長に掛け合う。
ところが所長は、その話について一切聞く耳を持とうとしなかった。
そればかりか、トミーの作り話しに騙されているだけだと、アンディを一蹴するだけだった。
真実が判明したのにも関わらず、アンディにとっても、観客にとっても、どうしようないほどの憤りが生まれる場面だ。
当然ながらアンディは反抗心を燃やし、何もしようとしてくれない所長に対し『あなたは愚純だ』という侮辱的な言葉を発する。
アンディのその言葉に意表を突かれ心外に思った所長は、怒りをあらわにし、罰としてアンディを懲罰房に入れてしまう。
そして、当のトミーは、刑務所内で受験した高校への進学が決まった後に所長に暗殺されるという悲劇に見舞われる。
何とも不条理極まりない所業であり、辛いシークエンスだ。
ここまで見れば、アンディが2ヶ月間という長期間入れられていた懲罰房から出てきたときに、復讐心を携えてきても良さそうである。
しかし、アンディにその兆候はなかった。
そもそも論として、アンディには怒りの心が内在していたとしても復讐を考えるような人物だろうか?
おそらくそれはない。
なぜなら、アンディはもともと、ホモセクシュアルのボグズたちに襲われても復讐することをしなかったからだ。
ボグズたちと戦っても、それはあくまで自分を守るために抵抗をしたに過ぎない。
例えば、誰かと共闘して打ち倒すことも可能ではあったとは思うが、それをしようとはしなかった。
これは間違いなくアンディには復讐心という心を持ち合わせていないという証拠である。
アンディには、感情の抑えが効かずに行動してしまう一面があるにはあるが、妻の愛人に対し銃で脅すような野蛮なことは出来ないのだ。
アンディには実に大きな寛容性があることを伺わさせる。
つまり、これが意味するに、アンディにとって復讐とは何の意味もないということだ。
そしてそれに代わるのが、アンディが常に求めていた『希望』である。
希望があればどんな状況にいたとしても自分自身を救う手立てとなり、精神的な苦痛からも解放され豊かであると思える。
アンディは復讐よりも希望を選んだのだ。
観客から見れば、アンディがただ単に復讐に身を燃やすタイプであればそれでも納得がいくが、アンディはそのような正当性を欠くようなことをしない。
そうした、正しい人間性をアンディが持っているからこそ、観客はアンディの魅力に心を奪われるのだろう。
解明されなかったアンディの一つの謎

『ショーシャンクの空に』のアンディには一つだけ不可解なことがある。
知っての通り、アンディは結果的に無罪の罪でショーシャンク刑務所に強制収容されることになってしまったが、その際に別の犯罪を犯した男たちも同時に入所されていたことを覚えているだろうか。
そうした新人たちは、所長からの絶対的な権力の前にひれ伏せられ、看守の執拗なヤジを受けながら、これからのムショ暮らしを始めることになるが、その初日の夜を新人の誰かが我慢できずにむせび泣くのが通例だという。
そして、それについて先輩囚人たちが賭けをし、何とか自分が賭けた囚人を泣かせたいため独房内でいじりだすのだ。
耐えきれなくなった新囚人は、辛い現実の前に泣き出すことになり、先輩囚人の賭けが成立することになるが、今回はばつが悪かった。
泣き出した囚人がそのまま大きく騒ぎだしてしまい、ついにはハドレー率いる看守たちを呼ぶ羽目になり「静かにしろ!」と怒鳴られてしまう。
しかし、その男は泣き止むどころか、自分は無実だと主張したためハドレーに殴り倒されてしまう。
ただ、殴り倒されるだけならケガだけで済む話だったが、翌朝、賭けをしていた囚人たちが朝食の会場で新人の容体を診療室担当から聞いたところ、その男は死んだという残念な知らせを受けることになる。
それを聞いたその場にいた全員が絶句することにはなるが、その際にアンディも近くにいたことで、ヘイウッドに「彼の名前は?」とその死んだ男の名前を知りたがった。
アンディにとって、その死んだ男は会話もしたことがない赤の他人であり、その男に特に思い入れなど何もないはずである。
ここで少々脱線するが、映画の中で出てくる『人』『セリフ』『もの』などは何かしら因果関係を持たせることが多い。
誰かがボソッと言ったセリフやパッと画面内に映ったものが、後からストーリーの中心として扱われることも少なくない。
この映画でもそのような鍵となるものがいくつかある。
一番分かりやすいのは所長の部屋に飾ってある刺繍ではないだろうか?
所長の奥さんが作ったという刺繍には『主の裁きは下る いずれ間もなく』という言葉が綴られている。
この言葉の意味を捉えようとするのなら、当初は刑務所という場所がら囚人に対する言葉であると考えるが、実は汚職を繰り返した所長に対する皮肉の言葉でもあった。
このように、映画に出てくる鍵となるものは何かしら物語の中で因果関係を持たせている。
ここで、先ほどのアンディのシーンに戻り「彼の名前は?」というセリフを考えてみる。
アンディのような主人公が発する言葉には、重要な意味が込められていることが多々あるので、観客はこの殺されてしまった男に「何か意味があるのか?」と考えることになる。
しかし、この場面はおろか最後まで死んだ男の名前は分からないまま終わりを迎えることになる。
では、なぜアンディは殺された男の名前を聞こうとしたのだろうか?
アンディの性格性を表すため
アンディが殺された男の名前を知りたいというセリフには、アンディの性格性を表すことにつながる。
たとえ、赤の他人であっても殺された男が『どのような人物だったのか?』と気にするような性格であれば、アンディには慈悲深い心があると観客は感じることになる。
このシーンでは、観客にはまだアンディが有罪なのか無罪なのかが判断できないからだ。
せめて、殺された男の名前を知りたいというセリフを発することで、アンディの性格性を少しでも表すようにしているわけだ。
仲間と話すきっかけにするため
ここは、アンディが初めてこれから仲間になる囚人たちと話をするシーンである。
もし、ここでアンディの会話がないとこのシーンを作る必要性がなくなってしまう。
また、劇中ではアンディは昨日初めて刑務所に来たところであり、刑務所に来て初めて自分から発する言葉である。(この前にブルックスからの質問に答えてはいるがこの場では無関係なので)
アンディの性格性とも重なることになるが、ここで言うセリフには『重み』が必要だ。
アンディがたとえ無罪であっても、度重なる悲劇に見舞われてきたのは事実であり、いきなり軽い話をしてその場を賑やかにすることなどできるわけがない。
また、アンディが多少混乱している雰囲気や、作り手はあえて観客にまだアンディの素性を掴みとらせないことなども考慮にいれているのだろう。
そうしたアンディの複雑な気持ちを代弁する言葉として、あの「彼の名前は?」と言うセリフにしたと考えられる。
囚人たちの性格性を表すため
アンディにとってはショーシャンク刑務所は初めての場所であり、知っている人間など誰もいない。
つまり、アンディにも観客にも、仲間になる囚人たちの性格性もあらかじめ見せておく必要がある。
『囚人たちという者はどういう人物なのか?』を垣間見せるために、ヘイウッドに語らせ、アンディの疑問に対して「知ってどうするんだ?」という非常な言葉にしているわけだ。
この言葉により、誰かが殺されても、その者の名前を気にしないような囚人たちであるということが分かってくるわけだ。
以上の理由などが考えられるが、仮にこれらを差し引いた場合に、実はまた新たな疑問が生まれてくる。
それは、アンディが死んだ男の名前が分かったら何をしたかったのか?というものだ。
雷雨が見せる解放感

恵みの雨と言うように、雨は生物が生きるため、そして土壌をうるおすために絶対的に必要な資源であることは誰にでも分かる。
脱獄時、アンディは下水菅の中に身を投じ、レッドが語る460mという、匍匐前進という格好ではとてつもないほど長く感じる距離を進んだ。
そして、下水管から這い出た先には、川があり空からは大粒の雨を浴びることになる。
これはまさしく、アンディに恵みをもたらせたという意味であることは言うまでもない。
そして、激しく鳴り響く雷もまたアンディにとっては福音の一つだ。
アンディは下水管を石で割る際に音をかき消すために雷を利用したからだ。
雷がなければ、もしかしたら看守にバレていた可能性は捨てきれない。
さらに言えば、雷が放つ光のコントラストがここではビジュアルデザインとして功を奏しており、アンディが悲願の脱獄に成功したことをよりドラマチックにしていることは間違いない。
仮に、このシーンが雨も雷もないただの夜だったらどうだろうか?
下水管から出てきたアンディが、天に向かってバンザイをするが、しかし、その恰好は汚い汚物まみれの体でありどう見てもホラーのようである。
いくら月明りがアンディを照らしていたとしても、雷ほどドラマチックに見せることはできない。
アンディの脱獄には、雨と雷が不可欠であり、これらによって解放感あふれるシーンとなっている。
正に映画史に残る名シーンだ。
まとめ
『ショーシャンクの空に(The Shawshank Redemption)』というタイトルながら、その言葉だけではどのような映画かは想像が付かない。
しかし、見た後でその真意が分かる。
作り手の見事な手腕の賜物であると言える。
しかも、多くを語ってくれるレッドのナレーションにより、この映画は誰もがとても分かりやすい。
難解さというものは一切なく、観客にとってはとてもありがたい映画である。
余計なことを考えずにストーリーに没頭できる傍ら、大事なことはきちんと隠して最後に明かされるという、とてもドラマチックな構成にもなっていて、とてもスカッとする映画の代名詞だ。
このようなドラマチックな構成により、この『ショーシャンクの空に』は誰でも共感を覚えられる名作になっていると言えよう。
ここに一つの言葉を引用しておきたい。
人生とは劇的に演じられるものだ
社会学者:アーヴィング・ゴフマン(Erving Goffman)