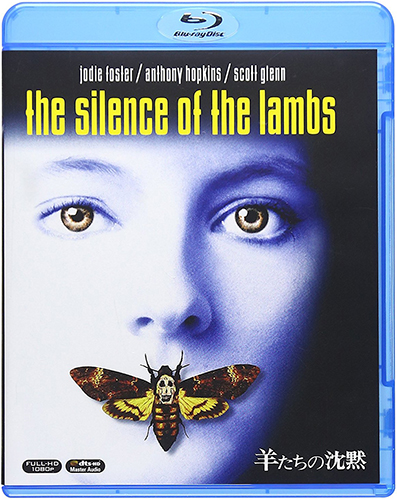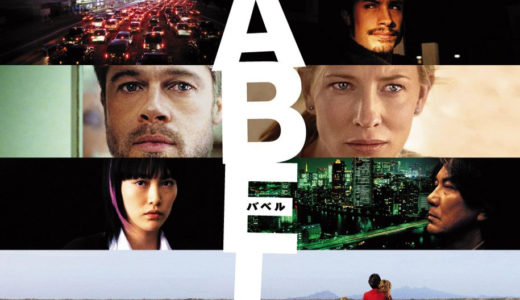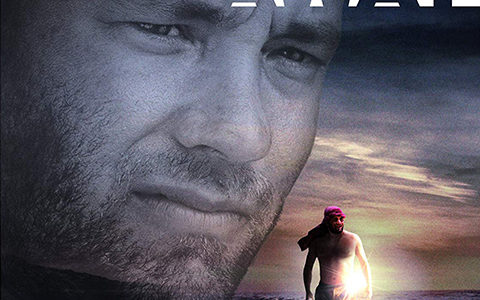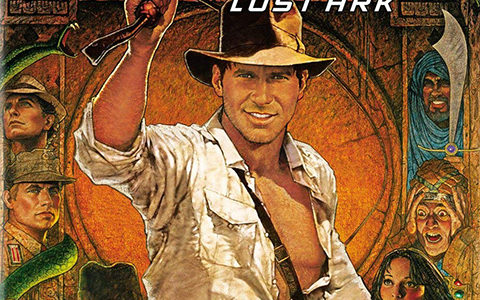はじめに
今回は『羊たちの沈黙(The Silence of the Lambs)』の解説です。
ネタバレしていますので、読む際はお気をつけくださいませ。
映画の概要
あらすじ
FBIの訓練学校に、まだ見習いの女性研修生がいた。
彼女は、心理学と犯罪学を専攻するクラリス・スターリングといい、毎日そこで訓練に励んでいたが、ある日行動科学課の現役捜査官であるクロフォードに呼び出される。
その理由は、クロフォードが行なっている監禁中の連続犯たちの心理分析で、一人だけ頑なに拒みつける男からの情報獲得のためだった。
その男の名は、元精神科医であるハンニバル・レクター。
『人肉事件』を引き起こした凶悪な異常者ではあるが、クラリスはそのレクターと会話を重ねる中で徐々に親交を深めることに成功する。
そして、バッファロー・ビルと呼ばれる、ある猟奇的殺人事件の犯人の手がかりをレクターから聞き出しながら、犯人を追い始めようとする。
ただし、それはバッファロー・ビルと同等かそれ以上に、レクターの精神異常性をも世間に知らしめることになるのだった。
キャスト・スタッフ・受賞歴
| 出演者 | ジョディ・フォスター、アンソニー・ホプキンス、スコット・グレン、テッド・レヴィン |
|---|---|
| 監督 | ジョナサン・デミ |
| 原作 | トマス・ハリス |
| 脚本 | テッド・タリー |
| 撮影監督 | タク・フジモト |
| 編集 | クレイグ・マッケイ |
| 音楽 | ハワード・ショア |
| 受賞歴 | 第64回アカデミー賞(作品賞、監督賞、主演男優賞、主演女優賞、脚色賞) |
| 公開 | 1991年 |
『羊たちの沈黙』を見るなら少しでも教訓を受けておきたい
今日の日本では、いきなり人を殺めようとする犯罪が後を絶たない。
何かニュースが飛び込んでくると、『拉致して殺害した』『車で歩道を突っ込んだ』『拳銃を奪って殺した』などと、当初から人を殺すことが目的になっている事件が多い。
どうしてそのような事件を起こそうとするのかは、やはり容疑者の精神鑑定が必要になるとは思うが、それにしてもむごすぎると言わざるを得ない事件にはひどく胸が痛む。
これは私の勝手な意見であり、決して犯罪を助長するわけではないが、それだったらまだ身代金目的の犯罪の方が救いがあるように思える。
そこには、容疑者から見れば警察や政府と要求に対し交渉できる余地が残されているし、警察の側から見れば人質を救える可能性があるからである。
容疑者と警察が話し、うまく折り合いがつけば、もしかしたらその時点で犯した罪について考え直すこともできるかもしれない。
しかし、人を殺すことが目的になってしまえば、当事者が被害に合わないよう、自分で身を守ってもらうしかない。
その時誰かがそばにいなければ、誰にも被害者を救うことはできないのだ。
脱線したが、『羊たちの沈黙』は、精神を患った犯人たちがどのような犯罪行為に至るのかを、一つのパターンとして教えてくれる。
どのように身を守れるかはその時の状況次第になってしまうが、道を歩いているだけでも必ずしも事件に巻き込まれないとは言い切れない世の中だからこそ、教訓の一つとして頭の片隅に入れておいても損はないだろう。
『羊たちの沈黙』におけるプロットとそれが与える観客への心理的影響
この映画を一言で言えば、『FBIがある殺人犯を追うために、別の殺人犯に操作を協力してもらう』というストーリーだ。
他の映画にも主人公が犯罪者と協力するストーリーは多々あるが、大抵が最初は嫌々引き受けることになるも途中で仲良くなり、最後に上手く解決したら無罪放免といった流れが多い。
しかし、『羊たちの沈黙』はそういう典型的な流れにはしていない。
あくまでレクターは精神異常者であり、犯罪者という構図のまま物語を終えることになる。
しかも、レクターはクラリスに協力するといっても簡単に協力しようとはしない。
レクターは牢獄に閉じ込められていることから『外の景色を見たい』と語ることもあるが、それは不可能だと悟っているため、刑務所から出して欲しいという要求はせず、レクターが求めるものはクラリスの個人的な話をただ聞きたいだけである。
そして、クラリスとの会話では常にクラリスを試し、もてあそぼうとする。
このレクターの要求とその会話こそが、映画を通して最も個性が際立つ部分であり、普通の犯罪物語からは一線を画しているプロットだと言える。
そして、何よりこのプロットのおかげで、観客にレクターの異常的な行動を注目させ続けることになり、あまりにもレクターが一般的な人の性格や言動とはかけ離れている精神性だということを知ることになる。
普段、私たちは重犯罪者と会話することはあまりない。
映画というものは、基本的に普段知らない世界や経験していないことを垣間見せることが一つの命題でもある。
この映画の命題は、凶悪犯罪者という存在がどういう性格なのか、どういう心境なのかを観客に知ってもらうことであり、それは功を奏している。
観客はなぜだか凶悪犯罪者であるレクターにとても興味をそそられ、レクターが見ているものや感じている世界を知りたいと思うようになっていく。
そして、レクターの極端な性格と思考を知っていくにつれ、観客はレクターの本当の恐ろしさを感じるようになり、強烈な印象を記憶に残すことになる。
極端なフレームで構成する極端な異質さ

この映画が、他のサスペンス映画と違う独特な雰囲気を表している点の一つとして、極端なフレームのショットが多いことが分かる。
レクターとクラリスの会話シーンで顕著に見られるそのショットは、カメラを直接見ているかのようにも見える、顔の超クローズアップだ。
これは俳優たちの顔を大きく見せることで、細かい表情や感情の動き、そして登場人物の異常性や深層心理を覗かせようとしているわけだが、それにしてもよくこれだけアップにしたものだと言える。
映画館の巨大なスクリーンで、これだけの大きさの顔と不気味なライティングを見せられたら、正に異様な雰囲気に飲み込まれるのは間違いない。
つまりこの手法は、俳優たちと観客が直接向かい合わせられることになり、レクターが語ることがクラリスだけでなく、観客にも向けられているという証明だ。
あなたがクラリスだったら、その場でどう考え、どう答える?と作り手が挑発しているかのようであり、よりこの映画の世界に没入せざるを得ない。
そして、このクローズアップが表現する意味は、観客に恐ろしいほどの緊張感を与える。
会話しているショットを細かく見ると分かるが、レクターの顔には段々とアップになっていくので、観客の目線に逃げ場がなくなる。
つまり、否が応でもレクターを凝視しなければならなくなるわけだ。
普段、家族や恋人でもない限り人の顔を間近で見ることはあまりないので、これだけクローズアップが多いと新鮮でありつつも、とても長く異質な時間がその場を支配することになり、レクターの絶対的恐怖感が襲ってくる。
クラリスとの出会いから分かる、レクターの存在意義

クラリスは、上司であるクロフォードからレクターに会うように促され、レクターが服役している精神病院に向かう。
そして、精神病院のドクターチルトンからレクターの異常性を聞きながら、独居房に単身入っていく。
そこには、レクター以外にも最も精神に問題のある犯罪者たちが囚われており、レクターの房までに、クラリスは二人の男を見ることになる。
この男たちは正に犯罪者らしく大声を出し暴れ、クラリスを挑発しようとするのだが、この犯罪者たちがいるおかげで、観客はレクターがさらに酷い人物なのかと想像させられることになる。
しかし、レクターはそのような大げさな立ち振る舞いはせず、堂々とまっすぐに房の中で立ってクラリスを迎え入れる。
観客にはパッと見、レクターがどちらかというと真面目であり紳士的にも映るが、予想よりも明らかに違う雰囲気が漂い始めるので、その佇まいに観客はとても不気味さを感じることになる。
そして、レクターとクラリスの会話が始まると、レクターはかなりの分析力豊かな思考回路を持っていると感じつつも、それは人間の普遍的な倫理観を超越した、どちらかと言えば狂気じみた存在だとわかり始める。
クラリスとの会話が続けば続くほど、だんだんとレクターの本性が現れ始め、異常性が垣間見えてくるからだ。
さらにはレクターがクラリスとの会話の中で不快感を覚えると、クラリスを見た目だけでプロファイリングし始める。
その結果、クラリスは「すごい洞察力。その直感力を自分に向ける勇気はある?」とレクターを挑発することになるが、この挑発がレクターをさらに不快にさせることになる。
そして、レクターは国勢調査に来た役員の肝臓を食べたとクラリスを怖がらせ、最終的にクラリスを子供のように扱いながら「お嬢ちゃん、帰りなさい」と言い放つ。
クラリスはもうレクターと話を続けられないと思い、仕方なく椅子から立ち、廊下を歩いて行くことになってしまう。
ここまで見れば、物語的には呆気ないほどの出会いと展開なのだが、注目すべき点はここからになる。
クラリスは、歩いて行った先の独居房にいた別の犯罪者であるミグズから檻越しに体液をかけられるという、とんでもない行為を受けることになるからだ。
クラリスはあまりに突然のことで動揺がおさまらないが、すかさずその光景を見ていたレクターは、クラリスにこっちに戻って来いと叫ぶ。
そしてレクターは、クラリスにミグズがしたことをわざわざ代わって謝り、レクターが過去に使っていた貸し倉庫の情報をクラリスに与え、「今のうちに早く行くんだ!」とその場を離れさせる。

なぜレクターはクラリスをわざわざ呼び戻し、情報を与えたのだろうか?
これには二つの理由が考えられる。
まず一つ目は脚本上の理由からで、ここでクラリスに何もない成果がないまま帰してしまうとその後のストーリーが続かないからだ。
クラリスを帰してしまえば、クラリスはまたFBIの研修に戻ることになってしまう。
これではストーリーが破綻する。
仮に、後からレクターがクラリスを刑務所に呼び戻すような設定にすることも可能だろうが、そうしてしまうと、あまりにも無駄なシーンをこの後に作ることになってしまう。
脚本家は、スマートにクラリスとレクターの物語を始めるさせるためにも、ここでレクターが持つ情報をクラリスに渡すようにしたかったわけだ。
二つ目は、レクターのキャラクター性をはっきりさせる必要があるためだ。
クラリスと会話をしたことで、レクターが只者ではない(正常ではない)ことが十分に強調はされていた。
従って、レクター自身として考えればここでクラリスを帰しても実は問題はない。
クラリスに「お嬢ちゃん、帰りなさい」と言うことからも分かるように、レクターにとってクラリスと会話することにはもはや興味がないからだ。
ところが、レクターはクラリスと同じ物語を司るキャラクターであり、そのキャラクターの性格や言動がきちんと示されている必要がある。
観客にとってその部分が欠けていると、キャラクターへの感情移入ができなくなり物語がつまらなく感じるのは避けられない。
そこでレクターに、ミグズの件を代わりに謝ることと過去の情報をクラリスに与えるという、少し正しい行為をさせることで、観客にレクターへの期待感をわざわざ持たせることにしたわけだ。
この期待感のおかげで、犯罪者であるレクターという人物についてもっと知りたいという欲求が観客には生まれることになる。
これら上記二つの理由により、レクターはクラリスを自分の元(独居房)へ一旦呼び戻し、物語を展開させるきっかけと、レクターの存在意義とキャラクター性を観客に伝えたわけだ。
クラリスではなくレクターに期待してしまうその構成

映画的に見れば、クラリスとレクターの会話を聞いているうちに、観客は心のどこかでレクターに期待をすることになる。
レクターがいくら凶悪な犯罪者であっても、主人公との間で悪意がない会話が重ねられ、協力するような行いを見せられていればその人物が気になってくるのは当然である。
そして観客は、これからレクターがどうなっていくのか、クラリスとどういう関係になるのか、もしかして刑務所を脱獄するんじゃないのか、などと作り手の思う通りに考え始める。
そして、その通りにレクターは警察官を殺害し、脱獄に成功することになる。
レクターは極めて異常な殺人者であるのに、なぜ、こうも簡単に『脱獄』に向かっていくストーリーにするのか?
これは、作り手が観客の心理を分かっており、しかもそれをあえて利用しているからである。
人は、なぜか身動きが取れないもの(ここでは牢獄)を見るとそこから出るのでは?と期待してしまう。
そして作り手は、正にこの観客の心理と期待感を巧みに操り、レクターとクラリスの会話を盛り上げながら、わざわざ刑務所から場所を移すことまでして、これから何かが起こるだろうという期待感を観客に煽っているのだ。
ただ、観客も脱獄の期待はしつつも「そんなに簡単にレクターを牢獄から出していいの?」とも当然考えることになる。
そこで、さらに作り手が考えたことは、ただ観客の期待感に応えるだけでなく、レクターはやはり殺人者であるという事実を知ってもらうのと同時に、精神異常者による殺人がどれだけ怖いものなのかを感じてもらうことにした。
それがあのレクターが行なった警官への残忍な殺害である。
『レクター』はなぜあのような残忍な殺人をしたのか?
物語として見たとき、レクターは食事を持ってきてくれた警察官にどうしてあそこまでの残忍な殺人をしたのだろうか?
警官をただ殺すだけならいざ知らず、わざわざ檻に縛り付けて腹まで裂き、内臓がさらけ出すほどの異常な行為までしている。
どんなに極悪人でもあそこまでやる必要はないと感じるはずだ。
一体これは何を観客に伝えているのだろうか?
レクターの人間性と残忍さを伝えたいのだろうか?
時系列で考えてみると、レクターは口に針金ほどの金属を隠していたのが分かるので、それならいつでも逃げ出そうと思えばできたはずである。
しかし、レクターにとっては逃げることよりもクラリスの話を聞くことを切望していた。
また、クラリスにはまだ自分(レクター自身)が必要であると分かっていたので、クラリスがいずれ来ることを予期していた。
そして、レクターの予想通りクラリスがレクターの元へ来ると、クラリスの深層心理にいる子羊たちの話を聞くのだが、ここである種の感情か、何かを思い出すことになる。
その感情は、レクターが親しみを込めるクラリスに、そんな酷い仕打ちをした牧場主が許せなかったという感情だろうか?
そして、そんな身勝手な八つ当たりだけで、警察官二人をあんなに残忍に殺したのだろうか?
いや、そうではない。
では、レクターの基本的立ち位置で考えてみよう。
レクターは基本的に檻に入れられている状態のままである。
クラリスは檻の中のレクターしか見ていないし、レクターも檻の内側からしかクラリスと話をしていない。
では、クラリスが話した納屋にいた子羊のことを、まさか檻にいる自分と同じように思ってしまったのだろうか?
いや、これも違うだろう。
クラリスが話す子羊とレクターは違う存在であり、レクターは自ら逃げ出すことができる。
ミグズが死んだ時にクラリスが「あなたもミグズと一緒ね」と言った時、レクターはミグズはもういないと語っている。
つまり、レクターは他の存在と自分を照らし合わせるようなことはしない。
それに、レクターが殺人をしても心拍数が常に一定であることから、子羊のように怯えることなどはないし、レクターにとっては、誰であろうと何の迷いもなく他の存在を排除することができる。
つまり、レクターはクラリスへの仕打ちに対し、八つ当たりして警官に怒りを振るっているわけでも、クラリスの子羊と自分を照らし合わせた感情で殺害したわけでもないことを示している。
ここで警官の殺害状況を見ると、ある種キリストの十字架を思わせるようにも見えるが決してそうではなく、蛾(が)が羽を広げて羽ばたいている最中に殺されたかのように見える。
蛾というのは当然、バッファロー・ビルが殺害した被害者の喉に詰めていたものだ。
この殺害現場の意味は、レクターがいた檻が蜘蛛の巣を表しており、その巣に捕まった(檻におびき寄せた)警官が蛾ということになる。
つまり、蜘蛛であるレクターが警官の腹を裂き蛾を捕食したという構図だ。
どうして、レクターがビルの犯行で使われた蛾をモチーフにした殺害表現をしたのかという心理までは定かではないが、ここで分かることは、レクターは感情論や道徳心抜きに人を殺害でき、それはある種自然の摂理のような解釈を持って行なっているということだ。
必ずしも証拠というわけではないが、レクターが殺人をする前にクラリスがチルトンに連れ去られる際の部屋全体のワイドショットが映る。
このショットが、あまりにも不自然に有刺鉄線を映しており、まるで罠にかかる虫を待っているかのようなメタファーになっているのだ。
サスペンスを盛り上げる編集手法

『羊たちの沈黙』も例に漏れず、サスペンスでよくある効果的な編集手法を用いている。
それは、FBI捜査官であるクロフォードが、まだ名前不詳だった容疑者の名前がJAME GUMBだと分かったシークエンスから始まる。
クロフォード率いるFBI捜査官たちは、JAME GUMBの家を特定し、これからの逮捕のために家の周りを静かに包囲していく。
時同じくして、殺人犯であるバッファロー・ビルと、囚われたキャサリンがいる家の中の様子も映り、キャサリンがビルの犬を井戸の下に奪ってしまったことが分かり、ビルが怒りをあらわにしている。
FBI側はピザの出前を受けたという仮定で、家のベルを鳴らす。
すると、ビルの家の中では一般の家庭では聞くことがないようなけたたましい音が鳴り響く。
ビルは逆上していてこれからどうなるか分からない混乱状態にあり、FBIは犯人を追い詰め逮捕の瞬間がすぐそばまできていると分かるという状況だ。
観客誰もが「ビルが逮捕される」と思うが、もちろんそうはならない。
FBIがドアを破り突入していった家には誰もおらず空き家であり、バッファロー・ビルの家に入っていくのは単身のクラリスだったからだ。
このように、状況を交互に映していく編集手法は『同じ時間・違う場所』を表すカットバックという手法を用いており、観客が持つ感情の対比が生まれ、緊張感を出しやすい。
そして、この緊張感はあくまで前座であり、観客が一旦ここでふっと気が抜けた直後から、また一気に緊張感を走らせることに一役買う。
何せ、クラリスの目の前にいる男こそが、殺人犯のJAME GUMBだからだ。
そして観客はクラリスに対し勝手にこう思い始める。
「その男が犯人だぞ!クラリスだけで大丈夫なのか?誰も応援は呼ばないのか?」と。
しかし、そんな観客の言葉が届くわけもなく、クラリスは自分一人でGUMBの家の地下室に入っていってしまう。
このせいで、観客はクラリスと一緒に殺人犯と対峙しなければならなくなり、嫌が応にもこれから起こるであろう恐ろしさを体験することになる。
上記のカットバックはよく使われる手法であり、他の映画でも見られることも多いが、サスペンスを盛り上げる上でとても効果的だ。
『羊たちの沈黙』のメッセージとは?
『羊たちの沈黙』は、そのまま見ても内容自体は分かる作品ではあるが、哲学的な思想も多く含まれていて、きちんと登場人物たちの裏の心理まで理解しようとすると難解になる。
では、『羊たちの沈黙』のメッセージとは何か?
猟奇的犯罪の恐怖?精神異常者たちの人格を知ること?
レクターが語るように、一貫して『残忍性』だと考えても良いかもしれない。
『レクターの倉庫にあった生首』『バッファロー・ビルの殺人と皮剥ぎ』『レクターの警官殺し』『クラリスの容赦ない発砲』まであるからだ。
しかし、レクターはクラリスにこう語っている。
「バッファロービルが人の生皮を剥ごうとする本質は何だ?」と。
ということは、バッファロー・ビルのように『切望』することが、『羊たちの沈黙』のメッセージだろうか?
いや、当然ながらそれは違う。
それはバッファロー・ビルの本質であり、この映画の主人公であるクラリスには関係がない。
物語として見た場合、メッセージはクラリスという主人公の内面を通したものでなければならない。
では、クラリスの本質は、犯人を追い詰めようとする『勇敢さ』であろうか?
確かに表面的にはそれを考えてもいいが、これも違う。
答えを先に書くと、『羊たちの沈黙』のメッセージは、意外にも『痛み』である。
それも、ただ殺人という外傷による意味の痛みではない。
クラリスが心に感じる心理的な痛みのことだ。
クラリスはこの物語で常に痛みを、心に傷を負わせられることになる。
クラリスは美人ということだけで、レクターが言う尊敬するクロフォードの性欲、ドクターチルトンの口説き、保安官や他の研修生からの視線を毎日受け続けている。
クラリスが、男から見られることを喜ぶことができる人物であれば問題ないのだが、これはクラリスにとっては言うなれば『視姦』であり、心への侵入と変わらない。
なぜなら、クラリスにとって男とは子供の時に亡くなった、愛する父親像でしかないからだ。
しかも、その後すぐに牧場主の羊を殺す残忍な光景を目にし、トラウマを持ってしまう。
クラリスは男に対し恐怖の度合いの方が強いのだ。
だから、男のそのような態度には喜べず、彼女が気づかないふりをしつつも男の視姦は心の痛みとなる。
さらにはレクターからの深層心理を引きずり出される執拗な尋問、バッファロービルによる生死を直面する恐怖など、クラリスは最後まで心に傷を、痛みを負うことになる。
すると思い出してほしいが、実はオープニング中にある言葉が示されており、それこそがこの映画のメッセージだと分かることになる。
オープニングでは、クラリスはFBIの訓練用のトレーニングコースを走っていた。
そして、クラリスが職員に呼び止められた後、木が映ることになるが、そこに貼り付けられていた言葉こそが正にそれである。
『HURT, AGONY, PAIN, LOVE IT』という言葉だ。
意味は『痛みを愛せよ』であり、詰まるところ『痛みを乗り越えろ』ということである。
これが『羊たちの沈黙』のメッセージだ。
『羊たちの沈黙』は、映画の構成から見れば、初見では表面的なことしか理解できずに終わってしまうことの方が多い。
しかし、本質を理解しようとするとその難解さから舌を巻くしかなく、しかもその答えは最初に示されているという盲点を突かれる始末だ。
原作者は相当の頭の持ち主であることが分かる。
ただその一方、決して軽蔑するわけではないが、クラリスへの執拗な攻撃を見てしまうと、原作者自身、女性に対しだいぶ片寄った心理があることを伺わせる。(本当は違うと思いますがw)
まとめ
『羊たちの沈黙』を見ると犯罪者たちの特殊性、偏執的な態度などから多くの異常的な側面を見せられる。
バッファロー・ビルがどうして作られてしまったのか、どうしてそのようになっていったのかはレクターが話してくれたが、決して生まれた時からそうなったのではないことが分かる。
ビルにはいくつかの抑制を受けることになりそれらが重なったことで、殺人をしてでも自分の望みを叶えていくという変質性が生まれてしまっていた。
つまり、犯罪は常に身近に起こり、何が引き金になるか分からないものであるということを伝えているようにも思う。
冒頭に述べたように日本でも死体遺棄事件など、異常的な犯罪も多発しているので自分も注意しつつ、あなたも巻き込まれないようご注意を。